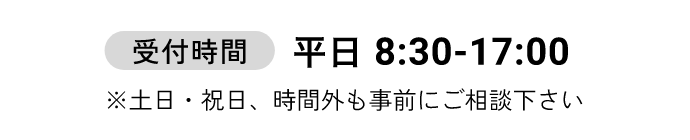統合失調症の方と適切に関わるためには、その人の「病識(自分が病気であるという認識)」の有無によって接し方を変えることがとても重要です。以下に、病識がある場合とない場合に分けて、寄り添い方や付き合い方のポイントをできるだけ詳しく解説します。
【1】病識が「ある」場合の関わり方
病識がある方は、自分が統合失調症であることを理解し、治療の必要性もある程度認識しています。このような方には以下のような配慮が効果的です。
1. 尊重と対等な関係を大切に
・「患者さん」として扱うのではなく、一人の人として対等に接する。
・病気について話す際は、プライバシーや気持ちに配慮しながら、相手の理解や考えを尊重。
2. 症状を否定しない
・幻聴や妄想などの症状が出ても、「それは違う」「気のせいだよ」などと真っ向から否定せず、「そう感じるんですね」と共感的に受け止める。
・ただし、現実検討能力が保たれている場合は、少しずつ「現実的な見方」への助言も可能。
3. 治療・服薬のサポート
・通院や服薬の継続をさりげなく応援する。「ちゃんと飲んでる?」ではなく「調子どう?薬は合ってる感じする?」などの自然な聞き方がよい。
・「治療を頑張っていること」を認めて、自己肯定感を高める関わりを。
4. 負担をかけすぎない関わり
・無理に励ましたり、将来の話を押し付けたりせず、本人のペースに合わせて関わる。
・疲れやすいこと、刺激に敏感であることを理解し、穏やかな環境を心がける。
【2】病識が「ない」場合の関わり方
病識がない方は、自分が病気であるという認識が乏しく、治療の必要性を感じていない場合が多いです。中には治療を拒否することもあります。接し方には特に注意が必要です。
1. 症状の否定・論破は逆効果
・幻聴や妄想などに対して「それは事実じゃないよ」「おかしいよ」と否定すると、不信感を招き、関係が悪化します。
・たとえば「そう思っているんだね」「怖かったね」と感情に寄り添う言い方が大切です。
2. 共感的理解を重視する
・「あなたが今感じていることを理解したい」という姿勢を見せると、少しずつ心を開きやすくなります。
・会話の目的は「説得」ではなく「信頼関係の構築」と考える。
3. 安心感を提供する
・「自分の味方がいる」と感じてもらうことが、最初のステップ。
・決して急がず、安心できる関係作りを優先。
4. 生活リズムの支援や環境調整から
・いきなり治療をすすめるのではなく、まずは睡眠・食事・清潔など基本的な生活習慣を整える支援から始める。
・その中で自然に医療との接点ができるよう働きかける。
5. 信頼できる第三者の活用
・家族や周囲の人だけで関わるのが難しい場合は、保健師、精神保健福祉士、訪問看護、地域包括支援センターなどの支援を頼る。
・本人が信頼する第三者の存在があると、受診や服薬に結びつきやすい。
【共通して大切なこと】
◉「回復志向」の関わりを
・「この人はよくなっていく」と信じることが、本人にとって大きな支えになります。
・小さな変化や努力を見逃さずに声をかけて、本人の自己効力感を高めることが重要です。
◉「待つこと」「見守ること」の価値を知る
・無理に変えようとしない。待つことも支援のひとつです。
今後は、「家族」「友人」「職場の人」「支援者」など、立場ごとの対応方法も考えていきたいと思っています。