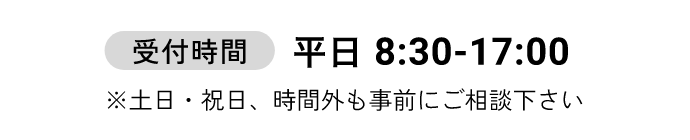統合失調症の方が障害年金を申請する際、特に「病識(自分が病気であるという認識)が乏しい・ない」ケースでは、以下のような注意点や盲点があります。障害年金の申請は「書類審査」が中心であり、本人の申立内容や診断書の記載に大きく依存するため、病識の有無は申請の成否に大きく関わります。
✅【注意点・盲点】一覧
1. 初診日の特定が困難になる
■ 理由:本人が病気である自覚がないため、受診歴を正確に記憶していないことが多い。
■ 対策:
・家族や支援者からの聞き取り。
・カルテ開示やレセプト情報の請求(医療機関や健保組合)。
・他院紹介状・診療情報提供書の確認。
2. 病歴・就労状況等申立書(病歴申立書)の記載が困難
■ 理由:本人が症状を軽視・否認していたり、幻覚妄想の内容が現実と混在していて正確な記述ができない。
■ 対策:
・家族、支援者、相談支援専門員、訪問看護師などの協力を得て代筆。
・過去の手帳申請書類、通院記録、就労支援記録などの活用。
3. 診断書に症状の重さが正しく反映されないリスク
■ 理由:
・患者が外来時に「元気にふるまう」「自分は問題ないと言う」ため、医師が実態を把握しきれない。
■ 対策:
・医師に日常生活の状況(家庭内・地域・就労状況)を支援者が伝える「参考資料」作成。
・家族や支援者が診察に同行して医師に伝える。
・医師への「診断書作成依頼書」や「生活状況メモ」を添える。
4. 「生活障害」の程度が客観的に伝わりにくい
■ 具体例:
・幻聴や妄想によって日常生活に著しい支障が出ているが、本人は「普通に暮らしている」と主張する。
・外見上は身だしなみが整っていて、周囲から見て障害がわかりにくい。
■ 対策:
・家庭内での支援内容(日常の声かけ、金銭管理、服薬管理等)を詳細に記録。
・支援者が客観的に記載した文書を添付(例:生活状況報告書)。
5. 審査で「就労可」と誤認されやすい
■ 理由:
・実際には就労できていない、もしくは短期離職を繰り返しているが、履歴書上は「働いていた」と誤解される。
■ 対策:
・雇用主や就労支援施設から「短期離職の背景事情」などを書面でもらう。
・ハローワークやB型事業所等の就労支援記録を提出。
6. 本人が申請に非協力的(または拒否)
■ 理由:本人が「自分は病気ではない」と思っているため、申請自体を拒否。
■ 対策:
・信頼関係のある支援者(例:精神保健福祉士や主治医)から申請の必要性を説明してもらう。
・成年後見制度や保佐人の活用(場合により申請代理可)。
・家族が代理人になる場合は「委任状」を準備。
7. 服薬・通院歴が断続的で「継続的な治療」がないとみなされる
■ 理由:病識が乏しいと、自己判断で通院・服薬を中断しやすい。
■ 対策:
・中断の理由を説明(例:陽性症状の悪化により通院拒否等)。
・支援者による介入の経緯(訪問支援や行政措置)を記録して提出。
✅【申請を円滑にするための実務的ヒント】
1.申請は家族や支援者主体で進めるのが望ましい
・本人の負担を減らし、申請の精度を高める。
2.主治医に「障害年金の診断書」の書き方を理解してもらう
・精神科医でも年金の審査基準に不慣れな場合がある。支援者がフォローすることで、症状が適切に反映されやすい。
3.複数の情報源から客観資料を集める
・例:家族のメモ、就労支援記録、手帳申請時の資料、行政対応記録など。
✅【補足:障害年金での等級判断基準(精神)】
精神疾患での障害年金の等級判断は、以下の「日常生活能力の判定とその程度」に基づきます:
■ 適切な食事
■ 身辺の清潔保持
■ 金銭管理・買い物
■ 通院や服薬管理
■ 他人との意思伝達及び対人関係
■ 身辺の安全保持及び危機管理
■ 社会生活への適応(就労・対人関係)
本人が「自分はできている」と主張しても、現実に家族や支援者が代行している場合、それを正確に記録・説明することが審査で極めて重要になります。