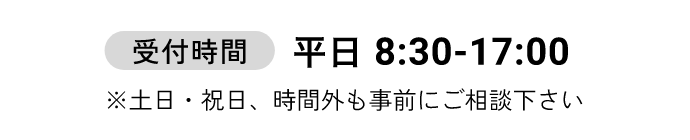双極性障害は、うつ状態と躁(または軽躁)状態を繰り返す疾患であり、うつ病とは異なる診断基準が必要です。そこで今回のコラムでは、実際に臨床ではどのように判別しているのかを、診察時のポイントに沿って、わかりやすく、かつ詳しく解説します。
1. 双極性障害の診断方法の基本的な流れ
(1)問診(診察の最も重要なパート)
医師は、患者さんやそのご家族に対し、以下の点を中心に詳しく聞き取ります:
・現在の症状(抑うつの有無、持続期間、日常生活への影響)
・過去の精神状態(気分の浮き沈みの有無)
・睡眠や食欲の変化
・衝動的な行動や金遣いの変化
・周囲とのトラブル歴(職場・家庭など)
・家族歴(特に気分障害の家系)
(2)診断基準に照らした評価
世界的には、DSM-5(精神疾患の診断と統計マニュアル)やICD-10(国際疾病分類)を用います。例えば:
・双極I型障害:躁状態が1回でもあれば診断される(うつ状態の有無は問わない)
・双極II型障害:軽躁状態と明確なうつ状態の両方が必要
2. 双極性障害とうつ病の「違い」と「診断時の見極めポイント」
💡 ポイント①:過去に「気分が異常に高揚した時期」があったか
■ 双極性障害では、躁状態または軽躁状態を経験します。
■ 典型的なエピソード:
・気分が異常に良くなりすぎる
・睡眠時間が極端に少なくても元気
・話し続ける、アイディアが次々と湧く
・自信過剰(自分は特別、何でもできる気がする)
・無謀な行動(金遣い、性的逸脱、仕事を突然辞める)
➡︎ これがあると「うつ病単独」ではなく「双極性障害」の可能性
💡 ポイント②:抗うつ薬の反応
■ うつ病の治療で抗うつ薬を使った際に躁状態になった経験があるかどうかを確認します。
・抗うつ薬を飲んで急に元気になりすぎた、テンションが上がりすぎた場合は、双極性の可能性が強い。
💡 ポイント③:発症年齢やエピソードの繰り返し
・双極性障害は比較的若年(10〜20代)で発症することが多く、エピソードが繰り返しやすい。
・一方、うつ病は30代以降で初発することも多い。
💡 ポイント④:家族歴
・双極性障害には遺伝的な影響が強く、家族に躁うつ病の方がいるとリスクが高い。
・うつ病でも家族歴はあるものの、双極性の方が顕著。
💡 ポイント⑤:患者さん自身が自覚していない「軽躁」
・軽躁状態は本人が「調子がいい」「普段より活発」と感じるだけで異常とは思わないことが多いため、家族や周囲の証言が重要になる。
・そのため、診察時には家族同席や家族からの情報提供がとても重要。
3. 医師が診断に使う補助ツール
・気分障害質問票(MDQ) や HCL-32 などのスクリーニングテスト
・経過観察(診断が一度ではつかない場合が多く、数ヶ月〜年単位での観察が必要)
・必要に応じて血液検査・画像検査(他の身体疾患との鑑別)
● まとめ:医師が診察で見る双極性障害の見極めポイント
| 観点 | 双極性障害 | うつ病 |
|---|---|---|
| 気分の変化 | 抑うつと躁(または軽躁)を繰り返す | 抑うつのみ |
| 発症年齢 | 若年期(10〜20代)に多い | 中高年にも多い |
| 抗うつ薬の反応 | 逆に躁転することあり | うつ症状が改善する |
| 家族歴 | 双極性の家族歴が多い | うつ病もあるが少なめ |
| 本人の自覚 | 軽躁を自覚しにくい | 抑うつを明確に自覚する |
● 最後に:
診断は一度の診察では決まらないことが多いです。医師は患者さんの長期的な経過を見ながら、慎重に診断を下します。そのため、患者さんやご家族が、日々の気分や行動の変化を記録して持参することは診断精度を高める大きな助けになります。