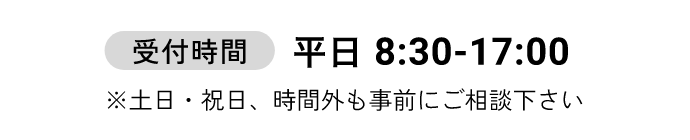「うちの子は双極性障害と診断されていますが、自分は病気ではないと思い込んでいて、通院も休みがちなんです」
「本人が “自分は働ける” と言っていて、障害年金の話しをすると怒り出してしまいます」
このようなお声を、ご家族や支援者の方からよくいただきます。
双極性障害をはじめとする精神疾患では、本人が自分の病気を認識していない(=病識がない)状態は決して珍しいことではありません。
しかし、障害年金の請求においては、診断書の取得、病歴の整理、生活状況の説明など、ご本人の協力が必要とされる場面が多く、病識の欠如は大きなハードルになります。
今回は、そのような状況でも申請を前に進めるために、ご家族や支援者がどのように関わり、どんな支援が可能かを具体的にお伝えします。
■ 「病識がない」とはどういうことか?
精神医学において、「病識」とは、自分の状態を“病気である”と理解し、自らの治療の必要性を受け入れる認識のことを指します。
しかし、双極性障害では次のような理由で病識が欠如しやすいとされています。
1.躁状態・軽躁状態では、「調子がいい」と感じる
→ 治療の必要を感じず、「なんで薬なんか飲まなきゃいけないんだ」と思ってしまう。
2.うつ状態では、「自分が悪い」と責める傾向が強い
→ 病気と認識せず、「こんな自分では障害年金なんてもらえない」と誤解する。
3.周囲からの指南に強い拒否感を示すことも
→ 障害年金の話題を出すことで関係が悪化することもある。
このように、病識がない場合、ご本人から必要な情報を引き出したり、申請に協力してもらったりすることが困難になります。
■ 障害年金請求における「病識のない本人」の問題点
病識のない状態でも、実際には日常生活に大きな制限を受けている方は多く、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、以下のような実務上の課題が発生します。
・ご本人が診断書の作成を医師に依頼しようとしない
・自ら病歴や生活状況をうまく説明できない、あるいは説明を拒否する
・「病気ではないから」と障害年金の請求そのものを拒む
・病歴・就労状況等申立書の内容と実態が一致しなくなる(例:実際には就労できないのに「働ける」と書いてしまう)
これらはすべて、審査での不支給のリスクを高める要因になり得ます。
■ ご家族・支援者にできること
ここからが本題です。
ご本人に病識がない場合でも、ご家族や支援者が適切に関与することで、障害年金の請求を進めることは十分に可能です。
以下に、具体的な支援方法を挙げます。
① 主治医に “家族からの情報提供” というかたちで実態を伝える
診断書は主治医が作成しますが、ご本人の申告内容に頼るだけでは、実態が十分に反映されないことも多々あります。
その際に有効なのが、家族や支援者からの客観的な生活実態の報告です。
・家族から生活状況や行動パターンを医師に伝える
・書面(観察記録、生活日誌など)で医師に渡す
・通院同行時に医師へ状況をそっと補足する
これにより、医師はより実態に即した診断書を作成しやすくなります。
② 「病歴・就労状況等申立書」作成を、第三者視点でサポート
病歴や日常生活の困難さを記すこの書類は、請求書類の中でも非常に重要なものです。
ご本人が協力的でなかったり、記憶が曖昧だったりする場合は、ご家族や支援者が代筆・補助することが可能です。
・ご本人が話した内容をもとに、過去の出来事を時系列で整理
・客観的事実(通院歴、退職歴、入院、支援機関とのやりとり等)を明記
・ご本人の生活上の困難を“具体的な行動レベル”で描写(例:「毎朝着替えるのに30分かかる」など)
これにより、本人が病識を持たない状態でも、障害の実態を審査側に伝えることができます。
③ ご本人との関係性を損なわない伝え方
最も大切なのは、障害年金の請求を無理に押しつけないことです。
・「あなたには障害年金を受ける権利があるよ」と穏やかに伝える
・「治療のために安定した生活基盤が必要なんだ」と目的を共有する
ことで、障害年金=自分の無力さの証、という誤解をやわらげる工夫も必要です。
また、ご本人が受け入れやすい第三者(医療職、社労士、支援員など)を介して説明することで、感情的な抵抗を軽減することもあります。
■ 専門家のサポートの必要性
私は、元臨床工学技士として医療の現場で患者さんの治療やご家族とのコミュニケーションに携わってきました。
現在は、社会保険労務士として、障害年金の請求を専門に支援しています。
ご本人の病識がないケースでは、ご家族・支援者・医師・専門職(社労士など)の連携が、不可欠な要素となります。
ときにその支援は「根気」も必要ですが、私たちが制度の道筋を整理することで、現場の負担を減らし、申請の実現可能性を高めることができます。
■ まとめ:病識がなくても、障害年金の請求は諦めなくていい
障害年金の制度は、本人の“自覚”よりも、実際の“日常生活上の困難”に基づいて認定されます。
したがって、病識がないからといって、障害年金の対象外になるわけではありません。
ご家族や支援者の気づきと、医療と制度をつなぐ支援者の存在があれば、
ご本人が気づいていない苦しみを、適切に制度につなげることができるのです。
「本人が拒否していて、もう無理だと思っていた…」
そんなときこそ、弊所の出番かもしれません。
どうぞ、一度ご相談ください。
筆者紹介
吉澤 健一
元臨床工学技士/医療コーディネーター/社会保険労務士
医療現場での経験と、障害年金の請求代理の専門的知識を活かし、精神の障害や肢体の障害、内部障害の方々に寄り添ったサポートを行っています。双極性障害をはじめとする精神の疾患で「どう動いていいかわからない」と感じたときは、まずはご連絡ください。
https://odawara-shougainenkin.com/contact/