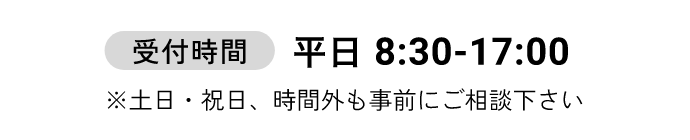肢体の障害と聞くと、交通事故や外傷によって手足が動かなくなるケースを想像される方が多いかもしれません。しかし実際には「進行性の神経・筋疾患」によって徐々に身体機能が奪われていくケースが多いのも実情です。
そこで今回のコラムでは、代表的な三つの疾患 – パーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィー – を取り上げ、各疾患の説明から日常生活への影響、そして関連する諸制度へのつなぎ方までを解説します。
1.パーキンソン病
パーキンソン病は、中脳の黒質という部位で神経細胞が減少することにより、体をスムーズに動かすための仕組みが障害される病気です。
👉 初期には
・手の震え(安静時振戦)
・歩幅が小さくなる(小刻み歩行)
・筋肉のこわばり(固縮)
・動作が遅くなる(動作緩慢)
といった症状が現れます。
👉 進行すると・・・転倒のリスクや嚥下障害が増え、着替え・食事・移動など日常生活動作の多くで介助が必要になります。加えて、便秘や睡眠障害、気分の落ち込みといった非運動症状もQOLに影響を及ぼします。
2.ALS(筋萎縮性側索硬化症)
ALSは、筋肉を動かすための神経(運動ニューロン)が障害される進行性の疾患です。
👉 初期には
・手足の脱力
・筋肉の萎縮
・話しにくいや飲み込みにくい
といった症状が見られます。
👉 進行すると・・・歩行や手の使用が難しくなり、食事や呼吸の動作にも介助や医療機器が必要になります。進行のスピードが比較的速いため、早期からの生活支援や制度利用の整備が不可欠です。
3.筋ジストロフィー
筋ジストロフィーは、遺伝的要因により筋肉が徐々に壊れていく疾患群です。代表的なデュシェンヌ型(DMD)では、幼少期から症状が始まります。
👉 初期には
・転びやすさ
・走る・階段を昇る動作の困難さ
・下肢を中心とした筋力低下
が現れます。
👉 進行すると・・・学童期から思春期にかけて車椅子が必要になり、さらに呼吸機能の低下も進行します。長期的なサポートが必須であり、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を及ぼします。
■ 医療と制度をつなぐ「橋渡し役」として
これらの疾患に共通するのは、「進行に伴って日常生活における動作の多くが制限される」という点です。医療の現場では治療や病状説明が中心となり、クライアント・ご家族にとって切実な願いは、“どう現状の生活を維持するか” ということではないでしょうか。
そこで重要になるのが、障害年金や介護保険、難病医療費助成などの各種制度の利用です。これらを早期から組み合わせて活用することで、安心して療養生活を続けることが可能となるからです。
私は元医療従事者、そして今は医療コーディネーター、社会保険労務士として医師の診断内容を制度利用につなげる工夫や、ADL(生活動作)の低下を関連する制度に適したかたちで代弁する「翻訳役」を担っています。これは、医療と制度の間に立つ者としての大切な役割だと考えています。
■ まとめ
難病や進行性疾患による「肢体の障害」は、身体機能の低下にとどまらず、日常生活全体を変えてしまいます。だからこそ、医学的な理解と同時に制度をうまく活用し、日常生活上の安心を確保していくことが必要になります。
私はこれからも、 ”医療と制度をつなぐ橋渡し役” として、クライアントやご家族が少しでも安心して日常生活を送れるよう支援を続けてまいります。