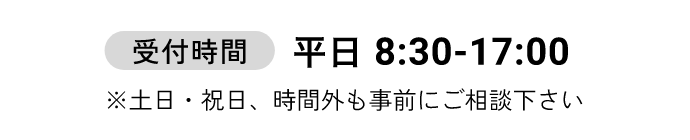診察室で主治医を前にすると、どうしても緊張してしまうものです。
「今日はあれを聞くつもりだったのに、言えなかった」
「一番つらい症状を伝え忘れてしまった」
「診察室を出た後に思い出して、もう一度戻りたいと思った」
こうした経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実際、医師の前では診察時間の制約や緊張感が重なり、自分が本当に伝えたいことを言葉にできないことはよくあることです。
しかし、病状は診察室の外でも確実に進行しています。だからこそ診察の場を「伝えたいことをしっかり共有できた」と思えるようにするためには、診察前の準備がとても大切です。
■ よくある「言い忘れ」の例
・最近強くなった症状を具体的に伝えられなかった
・薬の副作用について聞くのを忘れた
・日常生活で困っていることをうまく表現できなかった
・次の診察まで待てない悩みを抱えたまま帰宅した
👉 患者さんの声
「診察室を出てエレベーターに乗った瞬間、『あっ!言い忘れた!』と気づくことがよくあります。そのまま次の診察まで不安を抱えて過ごすのは、とてもつらいです。」
■ 実践チェックリスト ― 診察前にできる準備
診察をもっと有意義な時間にするために、次の工夫をおすすめします。
1.症状をメモに書き出す
・「いつから」「どんなふうに」「どのくらいの頻度で」起きているかを簡単にまとめる
・症状の強さを 1〜10 の数字で自己評価しておくと、主治医に伝わりやすい
・不安や気になる点も遠慮なく書き出しておく
👉 患者さんの声
「紙に書いて持って行ったら、主治医が『こうしてくれると助かります』と言ってくれました。診察中も落ち着いて話せました。」
2.質問リストを用意する
・主治医に確認したいことを箇条書きにして、紙にメモをして持参する
・「時間がなくても、これだけは聞きたい」という最重要事項を★印で目立たせておく
・リストを見せることで診察が効率的に進みやすい
👉 患者さんの声
「質問を順番に読み上げるだけでよかったので、頭が真っ白にならずに済みました。」
3.同席してくれる人を頼る
・家族や信頼できる人が同席することで、聞き忘れや伝え漏れを防げる
・自分がうまく話せない時に、代わりに説明してもらえる安心感がある
・医師の説明も一緒に聞けるため、理解の助けになる
👉 患者さんの声
「夫が同席してくれたおかげで、私が言えなかった症状を補足してもらえました。診察後も一緒に内容を確認できて安心でした。」
4.メディカルソーシャルワーカー(MSW)に相談する
・あらかじめ困っていることを整理してもらい、主治医に伝えてもらえる
・医療と生活の橋渡し役として、自分の思いを言語化してくれてサポートしてくれる
・主治医に直接言いにくいことを代弁してくれる
👉 患者さんの声
「自分ではうまく説明できなかった気持ちを、メディカルソーシャルワーカーさんが整理して伝えてくれたので、とても心強かったです。」
5.診察後の振り返りを習慣にする
・帰宅後に「今日伝えたこと・聞いたこと」を簡単にメモする
・言い忘れたことに気づいたら、次回の診察用メモに加えておく
・不安が強いときは、次回を待たずにメディカルソーシャルワーカーに相談してもよい
👉 患者さんの声
「診察後に思い出したことを、すぐにメモ帳に書くようにしています。次の診察のときに役立っています。」
■ 「全部話せた」という安心感を
診察室を出るときに「今日はちゃんと伝えられた」と思えることは、治療への前向きな気持ちや、日常生活での安心感につながります。
うまく話せないことは、決して珍しいことではありません。むしろ多くの患者さんにとって自然なことです。だからこそ、ちょっとした準備と工夫で、診察の質は大きく変わります。
診察は、医師からの説明を受ける場であると同時に、患者さんが自分の状況を伝える大切な「対話の場」です。準備をすることは、治療の効果を高め、安心して生活を続けるための第一歩になるのです。