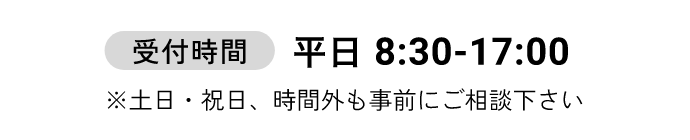医療現場でよく聞く「主治医ガチャ」という言葉は、患者が「運任せで相性や説明の丁寧さ、治療方針が大きく変わってしまう」状況を端的に表しています。患者側にとっては不安や不満につながり、医療の信頼にも影響します。本稿では、問題点を整理するとともに、現場で使える実践的な改善策と、主治医との相性が合わない・関係が崩れかけたときの対処法をわかりやすく解説します。
――――
■ 問題点とは(患者にとっての“ガチャ”が起きる主な理由)
・患者の希望とのミスマッチ:治療の目的(長期的QOL重視か、短期的症状抑制か)が医師と共有されていない。
・コミュニケーション不足:診察時間の制約や説明スタイルの違いで、患者が十分に納得できないまま治療が進む。
・医療の質・継続性への懸念:看護師の当直やローテーション、診療科間の連携不足で方針が変わりやすい。
――――
■ その背景(なぜ起きるのか?)
短時間診療、分業化された医療、専門分化による視点の偏り、患者参加の仕組みが不十分なことなどが重なって発生します。また、患者側が自分の価値観や生活優先事項をうまく伝えられないケースもあります。
――――
■ 現場でできる改善策(個人と組織の両面で)
1.セカンドオピニオンを制度として促進する
・患者が別の角度の意見を取りやすくすることで「選択肢」が見える化され、不安を減らす。
2.患者の意向を記録・共有するシステムの導入
・初診時・重要な転換点で「患者の優先順位(仕事・家庭・痛みのコントロール等)」を簡潔に記録し、チームで共有。
3.コミュニケーションの質を上げる訓練と時間設計
・アジェンダ設定(最初に「今日は何を一番話したいですか?」と確認)やティーチバック(患者に要点を言い返してもらう)を標準化。
4.医療コーディネーターやメディカルソーシャルワーカーの活用
・患者の橋渡し、情報の翻訳役、転院調整などを行う人材を活用すると、相性や引継ぎの問題が減る。
5.フィードバックと改善ループの確立
・患者満足度調査や診察後に短い振り返りを行い、個々の診療スタイルを改善する。
――――
■ 患者向け:相性が合わないと感じたらの実務的ステップ
1.自分の「困っていること」「大切にしたいこと」を整理する(紙に書くと伝えやすい)。
2.診察で率直に伝える(下の例文を参照)。まずは “修復” を試みる価値あり。
3.それでも合わないときは「セカンドオピニオン」を依頼する。紹介状や画像情報のコピーをもらう。
4.必要なら転院・主治医変更を検討するが、薬や検査の継続性は確保する(引継ぎ文書を作成してもらう)。
<患者が使える例文>
・「先生、治療の目的をもう一度整理したいのですが、私にとって一番大切なのは○○です。今の方針はそれにどう関係していますか?」
・「他の医師の意見も伺いたいので、セカンドオピニオンの紹介状をお願いできますか?」
・「申し訳ないのですが、検査結果や治療方針についてまだ不安が残るため、別の医師に診ていただきたいと考えています。紹介していただけますか?」
――――
■ 医師・医療機関向けの実務アドバイス
・初診で「患者の価値観確認シート」を使う(必ずしも長時間ではなく、要点だけで可)。
・診察の終わりに「今日の要点」を一言でまとめ、患者に復唱してもらう(理解確認)。
・チームの中で「患者の優先順位」を見える化する(電子カルテのワンラインメモ等)。
・相性の不一致が疑われたら、早めにメディカルソーシャルワーカーに相談し、転科・他院紹介の流れを整えておく。
――――
■ 関係が崩れかけたときの “処方箋”
1.感情的な対立を避け、事実(いつ、何が、どう感じたか)を整理する。
2.主治医に短時間の面談を申し込み、具体的な不安点を伝える(医療安全・治療継続の観点からも重要)。
3.医療機関の患者相談窓口でメディカルソーシャルワーカーに相談する。
4.セカンドオピニオンを速やかに取得し、必要なら転院や主治医変更の手続きを進める(ただし薬や検査は落ち着いて引き継ぐ)。
5.重大な医療過誤や説明義務違反が疑われる場合は、病院の苦情処理窓口や外部の第三者機関に相談する。
――――
■ 最後に(患者・医療従事者それぞれへメッセージ)
「主治医ガチャ」と言われてしまう背景には、制度的な制約とコミュニケーションのすれ違いが混在しています。患者側は自分の価値観を言語化して伝える準備を、医療側はそれを受け止める仕組みと態度を持つこと――この両輪が揃えば、“当たり外れ” ではなく「相互に選び合う関係」に近づけます。
――――
筆者:吉澤健一(社会保険労務士・医療コーディネーター/産業カウンセラー/元臨床工学技士)
専門学校卒業後、臨床工学技士として医療機関に勤務。その後、臨床を離れたものの、「医療を提供する側 (医療従事者としての目線)」と「医療の提供を受ける側 (患者としての目線)」の2つの視点を備える。平成26年度に社会保険労務士試験に合格後、医療機関にて5年間の障害年金の申請支援業務を経験。その後、令和3年1月に開業し、現在に至る。