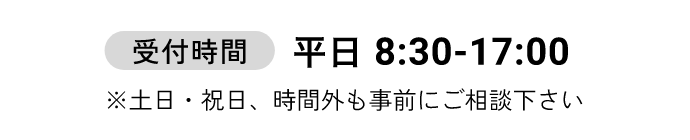「何度か病院を変えていて、通院も続かないんです…」
障害年金のご相談を受ける中で、双極性障害の方やご家族から、こうした言葉を聞くことは少なくありません。中には、初診から数年経って、ようやく「今の主治医とやっと向き合えるようになった」という方も。
今回は、双極性障害という病気が、なぜ通院の中断や転院を繰り返しやすいのか、その背景について、医療的・心理的な側面からわかりやすく解説します。
■「治った気がする」躁状態の罠
双極性障害は「うつ」と「躁」の波を繰り返す気分障害です。特に厄介なのは、「躁状態」にあるとき。
本人はとても元気で、むしろ「こんなに調子がいいなら、もう病院なんて必要ない」と思ってしまうことが多々あります。実際、躁状態にあるときは、睡眠も食事も取らずに活動的になり、自信に満ちあふれ、病識(自分が病気だという認識)を持ちにくくなるのです。
その結果、自己判断で通院を中断してしまったり、主治医と話がかみ合わず不満を持ち、転院してしまうケースも少なくありません。
■うつ状態になると、今度は「病院に行けない」
一方で、うつ状態に入ると状況は一変します。体が鉛のように重く、外に出る気力もなくなる。主治医の予約日が来ても、ただ布団の中でやり過ごしてしまう。
「通院に行けない自分が悪い」
「また怒られるかもしれない」
「何を話したらいいのかわからない」
こうした感情が重なり、結果的に長期の通院中断へとつながってしまいます。
■主治医との相性問題と病識のズレ
双極性障害の方は、病識があいまいな状態が長く続くことがあります。うつ状態のときは「助けてほしい」と思う反面、躁状態のときは「自分は正しい」と確信しやすくなります。
この認知のギャップが、医師との信頼関係を築く上で大きな壁となるのです。
「先生はわかってくれない」
「薬ばかりで話を聞いてくれない」
「今の自分には合っていない」
こうして主治医を変えようとする動機が生まれ、また新しい病院に行く。でも、診断の一貫性が保てず、障害年金などの手続きも困難になる…。そんな悪循環が起こりやすいのです。
■“続けること”こそが回復への道
双極性障害の治療は、「長い時間をかけて、自分の波と向き合っていく」ことが基本です。診断も経過観察も、数か月単位で見ていく必要があります。
だからこそ、一時的な気分や環境の変化で主治医を変えたり、通院をやめたりすることは、むしろ回復を遅らせる要因となり得ます。
無理に続ける必要はありませんが、「今の治療が合っていない」と感じたときは、主治医に率直に相談する、信頼できる家族や支援者と一緒に受診する、といった工夫が、転院や中断を防ぐカギになります。
■支援者ができること
ご家族や支援者ができるのは、「今の状態を一緒に見つめ、記録し、共有する」ことです。本人が気づけない病状の変化も、周囲の視点でカバーすることで、主治医に伝えるべき情報の“橋渡し役”になれます。
また、本人の自己否定感が強いときには、「通えたこと」そのものを評価し、安心して通院を継続できるよう支える姿勢も大切です。
まとめ:中断や転院は「その人の弱さ」ではない
双極性障害という病気の特性上、通院や治療の継続が難しいのはごく自然なことです。決して「意志が弱い」わけではありません。
「なぜ中断してしまったのか?」
「なぜ転院したのか?」
その背景を理解することで、ようやく本当の支援が始まります。障害年金の申請においても、こうした事情をしっかりと汲み取りながら、診断書や病歴・就労状況等申立書の中に、丁寧に反映していくことが求められます。
筆者:吉澤健一(社会保険労務士・医療コーディネーター/元臨床工学技士)
障害年金の請求を、医学的な視点と生活のリアリティを踏まえてサポートする「吉澤社労士事務所 メディカルサポート」代表。
ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。https://odawara-shougainenkin.com/contact/