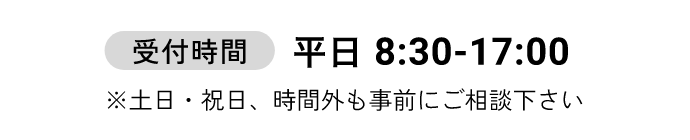双極性障害(躁うつ病)の初期症状と、それに対する本人の「病識(自分が病気であるという自覚)」の有無について、わかりやすく、詳しく解説します。
■ 双極性障害とは?
・双極性障害は、「躁状態(気分が異常に高揚する)」と「うつ状態(気分が著しく落ち込む)」を繰り返す気分障害です。
・発症年齢は10代後半〜30代前半が多く、初期には「うつ状態」から始まることが多いとされています。
■ 初期症状について
1. 初期の「うつ状態」の症状(もっとも多い発症パターン)
・理由なく気分が落ち込む
・仕事・学校・家事への意欲が著しく低下
・眠れない、または過眠
・疲れが取れない
・自責感や無価値感が強まる
・死にたい気持ちが出てくる
・集中できない、考えがまとまらない
💡 この段階では「うつ病」との区別がつきにくく、診断が難しいのが現実です。
2. 初期の「軽躁状態(ハイになってくる段階)」の症状(少数派の発症パターン)
・睡眠時間が少なくても元気
・おしゃべりが止まらない
・アイディアが次々と浮かぶ(が、実現性は乏しい)
・気が大きくなり、無謀な行動をとる(高額な買い物、投資、異性関係など)
・注意散漫、落ち着きがなくなる
・自分は何でもできると感じる(誇大感)
💡 この状態では、本人は「調子がいい」と思っており、病気とは認識しにくいため、問題視しません。
■ 病識はあるのか?
🔹 うつ状態の初期
・病識がある場合が多いが、「ただの疲れ」「性格の問題」だと思い込みやすい
・相談や受診にはつながりにくく、長期間放置されることもある
・家族や友人が気づくことが初期発見の鍵
🔹 軽躁状態の初期
・病識はほとんどない
・周囲が「ちょっと変だ」「テンションがおかしい」と気づくことが多い
・本人はむしろ「これが本来の自分」「人生がうまくいきだした」と感じる
・周囲が助言しても「余計なお世話」と捉え、医療機関の受診を拒むこともある
■ なぜ病識を持ちにくいのか?
・感情や行動の変化を「自分の性格の一部」と思っている
・病気によって認知の歪み(判断力の低下)が起きている
・病気の理解が乏しく、医療機関の受診に抵抗感がある
・初期では症状が日常生活にそこまで影響しないケースもある
■ 初期発見のヒント(周囲の人が気づきやすいポイント)
| 状態 | 気づきやすい行動変化の例 |
|---|---|
| うつ | 朝起きられない、遅刻が増える、涙もろくなる、服装に無頓着になる |
| 軽躁 | 急に社交的になる、出費が増える、話が止まらない、笑い方が変わる |
■ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期症状 | 多くはうつ状態から。軽躁状態で始まるケースもある |
| 病識の有無 | うつ状態では「何かおかしい」と感じるが、軽躁状態では病識はほぼなし |
| 診断の難しさ | 単なるうつ病やストレスと見分けがつきにくい。経過観察が重要 |
| 周囲の役割 | 本人よりも家族や職場の人が異変に気づくことが多い。受診のきっかけに |
■ 補足アドバイス
・本人が「自分はおかしい」と感じた時に、早めに相談できる環境づくりが重要です。
・初期は「調子が悪い」よりも「なんとなくおかしい」がヒントになることがあります。
・病識がないことを責めるのではなく、「一緒に確認してみよう」と寄り添う姿勢が大切です。