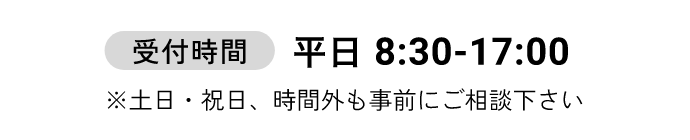■ はじめに
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血といった「脳血管疾患」は、リハビリや介護が必要になることが多い病気です。
急に発症して命にかかわることもあり、片麻痺(半身が動かしにくくなる状態)などの後遺症が残ることがあります。
このコラムでは、まず「脳血管疾患とはどんな病気か」をご紹介し、その後に「障害年金との関わり」を解説します。
■ 脳血管疾患とは?
「脳血管疾患」とは、脳の血管が詰まったり破れたりして、脳の一部がダメージを受ける病気の総称です。
代表的なものは次の3つです。
・脳梗塞(のうこうそく):脳の血管が詰まり、その先の脳細胞に血液が届かなくなって壊死する病気
・脳出血(のうしゅっけつ):脳の血管が破れ、脳の中に出血する病気
・くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ):脳の表面の血管が破れて、脳の外側に大量出血する病気
これらは突然起こることが多く、発症後すぐに適切な治療を受けられるかどうかで、その後の生活に大きな影響が出るものです。
■ 脳血管疾患の後遺症
脳は体を動かす、感じる、考えるなど多くの役割を担っているため、後遺症としての残存は人によってさまざまです。
主なものを挙げると:
・片麻痺(かたまひ):体の片側(右半身や左半身)が動かしにくくなる
・言語障害:言葉が出にくい、発音が不明瞭になる
・感覚障害:しびれや感覚が鈍くなる
・視野障害:視界の一部が見えなくなる
・高次脳機能障害:記憶力・注意力・判断力が低下する
👉 このように「手足が不自由になる」だけでなく、日常生活上でのコミュニケーションや労働・家事にも影響します。
■ 後遺症が日常生活に与える影響
脳血管疾患の後遺症は、日常生活のあらゆる場面に影響を与えます。
・一人で歩けない → 杖や車椅子が必要になる
・着替えや入浴が一人でできない
・食事に時間がかかり、場合によっては介助が必要
・職場復帰が難しくなる
👉 その結果、ご本人だけでなく、ご家族の生活も大きく変わることがあります。
■ 障害年金と脳血管疾患の関係
脳血管疾患による後遺症は、障害年金の対象になります。
ただし、障害年金は「病気や後遺症があるから自動的にもらえる」というものではありません。
実際には、
・障害年金の診断書に書かれる医学的な所見
・日常生活でどのくらい支障があるか(移動・食事・着替えなど)
・労働にどれだけ制限が生じてしまったか
こうした情報をもとに、専門的に判定されます。
👉 診断書の内容や、実際の日常生活状況の伝え方によって結果が大きく変わるため、注意が必要です。
■ まとめ
脳血管疾患は、発症後の日常生活に大きな影響を与える病気です。
その後遺症が日常生活に支障・労働に制限がある場合には、障害年金の対象となります。
ただし、受給の可否や等級は専門的な判断に基づいて決められるため、正しい知識とサポートが欠かせません。
弊所は、臨床工学技士として医療機関での勤務経験、そして医療コーディネーター、社会保険労務士として、クライアント・ご家族・医療従事者の ”橋渡し役” となるべく、障害年金の申請サポートを行っています。
👉 脳血管疾患後の障害年金の申請について不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせはこちら】https://odawara-shougainenkin.com/contact/