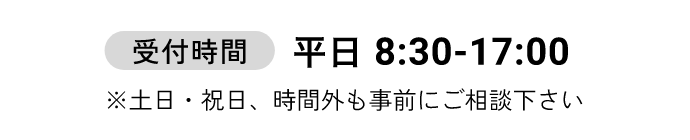「こんなに短くて、本当に肝心なところを診てもらえているのだろうか?」
外来受診のあと、そんな思いを抱いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。実際、1人あたりの診療時間が5分に満たないことも珍しくありません。「これで本当に大丈夫なのか?」と不安に感じてしまう気持ちも、よくわかります。
しかし、このわずか数分の診察時間の中で、医師は驚くほどの情報を処理し、重大な判断を下しているのです。
■ 一瞬で見極める“兆し”
診察室に入ってきた瞬間から、医師はすでに患者を診ています。
たとえば――
歩き方、表情、呼吸の仕方、皮膚の色、話すトーン、眼差し。こうしたすべての「非言語情報」をもとに、医師は頭の中で過去の症例や知識と照合しながら、病態の見極めを始めているのです。
これは、もはや経験と訓練を積み重ねた“直感”に近いもの。医師の脳内では、短時間で大量のデータが処理され、膨大な選択肢の中から「まず疑うべき病気」が絞り込まれています。
■ 質問の一つひとつに意味がある
診察中の医師の質問は、単なる雑談ではありません。
たとえば「胸が痛い」と言ったとき、
「いつから?」「動いたとき?安静時?」「深呼吸で悪化する?」などと矢継ぎ早に聞かれることがありますが、これは決して機械的なやり取りではなく、危険な病気を最短距離で除外または疑うための問いかけです。
つまり、医師はその場で「この症状の裏にある“見逃してはいけない疾患”が何か」を的確に絞り込む、極めて高度な推論を行っているのです。
■ 「大丈夫」と言うことの責任
医師にとって最も恐ろしいのは、「軽い症状に見えたが、実は重篤だった」という事態です。
たとえば、かすかな頭痛の背後にくも膜下出血が隠れていたり、一見風邪のような症状の陰に心不全が進行していたり――
医師は、そうした“軽症に見える重症”を常に警戒しています。
そのうえで、「大丈夫です」「様子を見ましょう」と言うとき、そこには“見落とさない自信”と“もしもの備え”が含まれています。
この判断には、知識、経験、洞察力、そして患者への責任がすべて込められているのです。
■ 私たちにできる“準備”とは
診察時間が限られているからこそ、私たち患者側にもできる準備があります。
・いつからどんな症状があるのかを整理しておく
・気になることをメモにしておく
・「一番つらいこと」や「気になっていること」を一言で伝える準備をしておく
これだけでも、診察の密度と質はぐっと高まります。医師が本当に必要な判断を、最短距離で下せるようにするための「協力」でもあるのです。
■ 5分間に込められた医師の覚悟
診察室で過ごす5分――
その短さに不満を感じるかもしれませんが、医師にとっては、そこでどんな決断を下すかが命に関わることすらあります。
私たちが目にするのは、氷山の一角。
その水面下では、医学的知識、豊富な経験、リスク評価、患者への責任感といった、さまざまな要素が総動員されています。
そのことを少しでも理解できたとき、「短いから不安」ではなく、「短いけれど、濃密で意味ある診察だった」と感じられるようになるかもしれません。
■ おわりに
「たかが5分、されど5分」。
その中に込められた医師の判断の重みを、私たちも正しく受け止め、限られた時間をより有意義に活用していきたいものです。
筆者紹介
この「お知らせ」は、元臨床工学技士であり、現在は医療現場を熟知した社会保険労務士として障害年金の申請支援に携わる筆者が執筆しています。
医療現場で命に向き合ってきた経験と、現在の「制度」と「暮らし」に寄り添う立場を活かし、クライアントやご家族、そして医療関係者との“橋渡し”となる情報を発信しています。
吉澤社労士事務所 メディカルサポートについて
弊所では、障害年金専門の社会保険労務士事務所として、特に医療的なサポートが求められるケース(肢体不自由・精神疾患・内部障害など)に注力し、受給の可能性を丁寧に見極めた上で、主治医への診断書の作成依頼から申請まで一貫してサポートを行っています。
また、元医療従事者の視点を活かし、医療機関との円滑な連携や、クライアントの想いが診断書に適切に反映されるよう支援することも特徴のひとつです。
医療現場と制度の“すき間”に悩む方に、寄り添える存在でありたいと願いながら、日々活動しています。
◆ お問い合わせ
障害年金の申請でお困りの方、または医療機関の先生方・支援者の皆さまからのご相談も承っております。
詳しくは、https://odawara-shougainenkin.com/contact/ から、ご連絡ください。